vol.
012
MARCH
2016
vol.012 / 特集
見えない視線
林口砂里|福原志保|甲斐賢治/北野央|森永邦彦|飴屋法水|津田直
例えばミツバチやモンシロチョウには紫外線が、マムシやハブには赤外線が見えている。もしも人間に違う生物の目を移植したら、今までとはまったく違う世界を生きることになるだろう。どうやら見えないものを認識することで、見えてくることがあるようだ。
宇宙、生命、距離、意識、言葉、時間。
6人の視線の先にあったもの。それは見えない世界を見るということ。
林口砂里|福原志保|甲斐賢治/北野央|森永邦彦|飴屋法水|津田直
言葉
人は、言葉で世界を認識している
飴屋法水
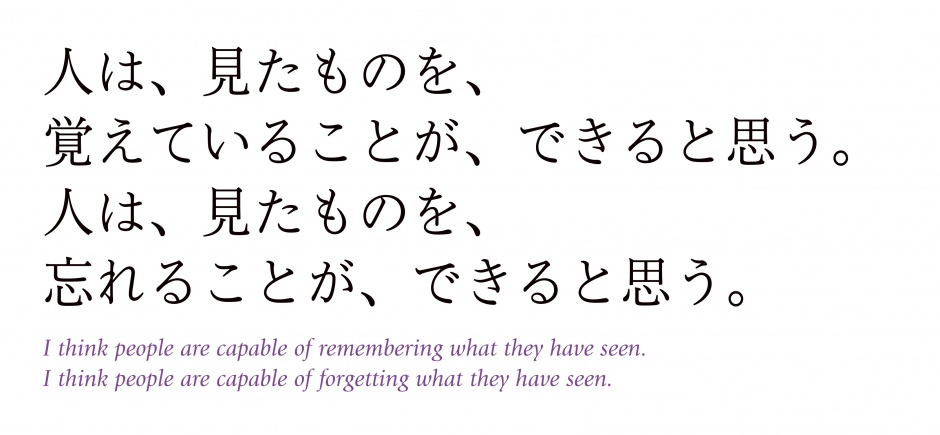
戯曲はテキストの状態で味わうものではなく、誰かが発語して初めて観客に届けられます。台本の時点では「圧縮」されていた言葉が、舞台上で、人の声で「解凍」されていくというか。だからせりふを書くときには、それが声に出したくなる、解凍したくなる言葉かどうかを考えます。
言葉のオリジナリティについて思うとき、「個性的な言葉なんてありえない」と感じたりします。コップを指し示す際に、「コッコ」と表現したら相手に伝わりませんよね。言語にはルールがあって、共通だからこそ伝わる。本質的に平凡なものであるはずです。
僕はしゃべるのが得意ではなくて、ずっと自分は言葉が苦手なんだと思っていました。でもそうじゃないかもしれません。犬を見て「犬だ」と感じたときには、すでに「犬」という単語を使って、分類して整理をしている。もっとグラデーションがあるはずなのに、「痩せて」「老いた」「茶色の」「犬」とか、言葉で分類しないと認識にならないんです。世界から、もやもやとした抽象的なものを受け取っても、言葉でしか具象化できない。表せない。だから創作でも日常でも、あらゆるシーンで、僕もどっぷりと言葉に依存しているんだと思います。
考えてみると、言葉にするというのは、物事をすごくつまらなくしている作業かもしれません。例えば犬は、どこにでもいる犬だから「犬」と呼べる。でもその犬は、たった一匹の犬です。また、愛という言葉の意味は、誰でも知っているし、きっと誰も知らない。知っているから言葉で話せるし、知らないから話し続けるのかもしれないですね。
言葉というのは、そういった二面性をもっている、とても不完全で不思議なものです。それはそのまま、作品というものが持ちうる「共通性」と「唯一性」というか、つまり矛盾そのものになるんだと思います。
編集・執筆:平林理奈/Playce



